日本の音楽シーンにおいて、94年頃から97年頃にかけて小室ブームとういうのがあった。
例えばTRFのように、もともとはジュリアナ東京から火がついてヒットしたものもあれば、元東京パフォーマンスドールの篠原涼子を使った『いとしさと切なさと心強さと』など、歌謡曲よりのものもあった。
リリースする曲のほとんどがミリオン、あるいはダブルミリオンを記録し、一躍、時代の寵児だったと言って、差し支えないだろう。
音楽プロデユーサーとしての彼の当時の狙いは、当時の若者の生活スタイルであった。
新曲が発売されればカラオケに向かい、クラブで踊るという層を、ターゲットにしていたという点にある。
筆者の音楽の聴き方もその例に漏れず、新曲が発売されればCDを買い、カラオケによく向かったものだ。
しかしインドア派だった筆者は、クラブに通うといった体験はあまりなかった。
当時、電気GROOVEなどのテクノファンだった筆者は、電気GROOVEのライブに行ったことがあるが、会場は完全にクラブと化していた。
エイベックストラックスと小室サウンドの融合が始まっているのを感じていた。
当初エイベックストラックスはジュリアナ東京から始まり、ディスコからクラブへ転換したあとも、ユーロビートなどのテクノ系ダンスミュージックを発売しており、まぎれもなく90年代はテクノ系のレーベルだったことを、発売されたCDから伺うことができる。
1995年のTRFの『Overnight Sensation」、1996年の安室奈美恵の『Don’t Wannacry』、1997年の同じく安室奈美恵の『CAN YOU CELEBRATE?』、 1998年のglobeの『Wannabe a dreammaker』らが、4年連続レコード大賞を受賞した。
間違いなくこの間は、小室哲哉が日本の音楽シーンを席巻していたといっても、過言ではないだろう。
このころ世界のミュージックシーンはどうだったのであろうか?
小室哲哉が日本の音楽シーンを席巻していたこの時期、世界のミュージックシーンもまた、様々な変革を迎えていた。
1990年代は、グローバルに見ても音楽ジャンルが多様化し、さまざまなスタイルが融合していく時代だった。
まず、アメリカではヒップホップとR&Bの台頭が顕著であった。
特に、2PacやNotorious B.I.G.といったアーティストが登場し、彼らの音楽は社会問題や個人の経験を反映する重要なメッセージとなっていた。
また、マライア・キャリーやブリトニー・スピアーズのようなポップアーティストも登場し、商業音楽の新たなスタンダードを築いた。
一方、イギリスではブリットポップが流行し、オアシスやブラーといったバンドが国民的な人気を博した。
彼らの音楽はアメリカのグランジやロックとは対照的に、英国特有のメロディと歌詞が特徴で、若者たちの間で強い共鳴を得ていた。
このように世界の音楽シーンは、ジャンルごとに異なる潮流が生まれ、国境を越えた影響を与え合っていたと言えるだろう。
日本においても、小室ブームはその中で独自の位置を占めていた。
小室サウンドは、テクノやダンスミュージックを基盤にしつつ、ポップなメロディやキャッチーなリフを取り入れたスタイルであり、これが日本の音楽ファンに受け入れられる要因となっていたのだ。
特に、カラオケ文化の普及と相まって、彼の楽曲は多くの人々に親しまれることとなった。
さらに、90年代後半にはインターネットが普及し始め、音楽の流通や消費の形態も変化しつつあった。
音楽の購入や発見がオンラインで行われるようになり、これがアーティストやプロデューサーに新たな挑戦をもたらした。
小室哲哉もその波に影響を受けつつ、次の時代に向けた音楽制作を模索していくことになる。
このように、90年代の小室ブームは日本独自の現象でありながら、同時に世界の音楽シーンの変化とも密接に関連していたのだ。
次回は、彼の音楽スタイルや影響力、そしてその後の展開について、さらに掘り下げていきたいと思う。


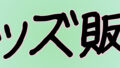
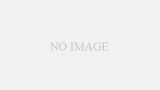
コメント