古今東西の著名人のアフォリズム(格言)の中から、筆者が感銘を受けたものをピックアップし、その感想を述べていきたいと思う。
解釈が多義的になってしまうこと、お許し願いたいと思う。
その1 哲学者たちは~: カール・マルクス
哲学者たちは世界を色々な仕方でただ解釈してきた。
しかし肝心なのは、世界の変革である。
カール・マルクス
感想
19世紀にプロイセンでリカード、アダムスミス、JSミルなどを学んだマルクスは著書『経済学・哲学草稿』などで、自分の好きな仕事もなかなかできず疎外され搾取されながら働かなければならない資本主義の問題を考え、現状を変えなければならないことをわかっていた。
しかし、のちに著書『ドイツイデオロギー』での中で、「共産主義とは理想とすべきある社会を指すのではなく、理想とすべき社会の実現のプロセスのことを指すのである」とも述べているように、後世レーニンやスターリンが実現したような、表向きだけ国民の富の平等を唱え、実質資本主義以上に腐敗し既に崩壊した、いわゆる共産主義とは異なっている。
すべての人にとって理想的であり、民主主義的な社会を実現することは難しいが、政治の役割が社会を永遠に微調整していかなければいかない。
そういった意味で、今日でもマルクスの言っていることは生きていると、筆者は考えている。
その2 生きることの意味と価値に~: ジ-クムント・フロイト
生きることの意味と価値について問いかけるようになると、我々は狂ってしまう。
なにしろ意味も価値も客観的に実在するものではないから。
ジ-クムント・フロイト
感想
人間の心理を自我、エス、超自我に分類したフロイトであるが、人間を突き動かす原動力としてリビドー(性的衝動)の実現、及びそのコントロールとしての超自我こそが、人間の生きる心理構造と考えていた。
彼のいう人類が生きる意味や価値は、著書『トーテムとタブー」の中で論じているエディプスコンプレックスの克服(近親相姦の禁忌)であると、少なくとも著者は思っていた。
しかし上記のアフォリズムを見る限り、とくにフロイトは人生に生きること、その意味を定義していなかったのではないかと、筆者はとらえる。
なぜなら、そこからあぶれ出た人の人生は無意味か、というニヒリズムに陥りかねないからだ。
すべての人間には十人十色の価値観や幸福感があっていい。
フロイトのこのアフォリズムをそうとらえることで、少し人生は楽にならないだろうか?
その3 簡潔さは究極の~: レオナルド・ダ・ヴィンチ
簡潔さは究極の洗練である。
レオナルド・ダ・ヴィンチ
感想
ルネッサンス期に活躍した画家であり科学者でもあり万能の天才であった彼とは、一見して好対照をなすアフォリズムに見える。
しかし、このことは『モナリザ』や『最後の晩餐』などを描く一方で、ヘリコプターの設計や人体の解剖などを行っていた技術者としての達観ではないだろうか?
1995年にマイクロソフト社のOS、WINDOWS95が世に発売された時の感動を今でも忘れられない。
今まではパソコン通信と研究機関等を結ぶ、ARPANETの高度なプログラミングによってしか実現できなかったコンピュータ通信が、世界中どこでもGUIグラフィックユーザーインターフェイスのクリック一つで実現できてしまう。
技術とは高度になればなるほど逆に使用する者にとっては実に簡潔になっていく。
その意味だと筆者はとらえている。



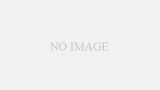
コメント