広義の定義においては、シンセサイザーなどの電子音楽器を使って創作された音楽の総称であるとされているが、それがどのように生まれ、世界や日本に浸透したのだろうか?
テクノポップの定義
まず、明確に分類できることではないかもしれないが、ここでは1980年代のアメリカで、ホアンアトキンスが命名したダンスミュージックにおける『テクノ』とは区別したいと考えている。
ホアンアトキンスやデリックメイらのデトロイトテクノ系のミュージックは、後にアメリカのシカゴ発のハウスミュージックと渾然一体化していき、日本においてはジュリアナ東京などで定着し、また世界的に一旦は別の潮流をたどるからである。
ここで筆者が強調したいテクノ、テクノポップは、それまで1950年代から60年代に活躍したドイツのカールハインツシュトックハウゼンや、フランスのブーレーズ、イタリアのノーノ等のクラシカルで実験的な電子音楽をポップス、あるいはロックとして大衆に広めた。
これまたドイツのクラフトワーク、アメリカのディーヴォ、日本のイエローマジックオーケストラ(以下YMO)などの、1970年代以降のアーティストのことである。
日本の音楽評論家、阿木譲は、クラフトワークのアルバム『人間解体』を聴き、それらを『テクノポップ』と命名したことで、名づけの親と謂われている。
日本のテクノポップミュージシャン『YMO』はどうだったか
1978年の11月にアルバム『イエローマジック・オーケストラ』でデビュー。
その翌年、アメリカでのデビューが決まる。
1979年に全米で『イエローマジック・オーケストラ』、『ソリドステイトサヴァイバー』のアルバムは大ヒットし、アメリカのみならずイギリスでもツアーが大反響を呼ぶなどし、その年の暮れの12月に日本で凱旋ライブを行う。
国内ではすでにYMOフィーバーが起こっていたそうだ。
ほぼ逆輸入である。
筆者にとってこれらのことは、ほぼリアルタイムな体験ではない。
90年代の筆者が高校生の頃、日本の電気グルーヴに興味を持ち、それに影響を受けたとされるYMOを90年代に聴き、シングル『中国女』、『テクノポリス』などに感銘を受け、それからのめりこむことになる。
聴いてみるとわかるのだが、これらはエレクトロニクスサウンドであるが、ダンスミュージックではない。
クラフトワークの『ネオンライツ』、『コンピュータラブ』などもそうだが、BPMが実に遅いがポップスであり、テクノカルチャーである。
結局日本国内においてYMOは、1978年から1983年の5年間で一旦は終わることになる。
そのあとの日本の音楽シーンはバンドブームが起こり、90年代前半はBeingが全盛期をなし、そのあとは小室ファミリーがブームを迎える。
2000年代からは宇多田ヒカルなどのニューR&Bが台頭し、もう2007年には初音ミクらのボカロ現象が始まる。
テクノポップは終わってしまったのか?
そんな僕らの懐古趣味を救ってくくれたのが、中田ヤスタカプロデュースのPerfumeだった。
Perfumeには多角的な楽しみが内包されている。
YMO時代のシンセサイザーとはけた違いに性能の良いデジタルシンセサイザーによるテクノポップサウンド、自明の事柄のようであるが3人のルックスの良さ、高度に洗練されたダンス、プロジェクションマッピングなどテクノロジーにによるライブステージの演出など、昔のテクノポップブームと単純に比較はできなさそうである。
インディーズ時代も含めると1999年にデビューしたPerfumeだったが、一躍脚光を浴びるようになったのが2007年の『ポリリズム』だ。
再び日本にテクノポップの熱いブームが訪れる。
その翌年2008年アルバム『GAME』を発売。
1983年のYMOのアルバム『浮気なぼくら』以来、実に四半世紀ぶりのオリコンチャート1位を獲得することになる。
その後2012年以降、およそ10年ほどのPerfumeは台湾、香港、韓国、シンガポールを皮切りに、ドイツ、フランス、イギリスにワールドツアーを展開していく。
190年代にくしくもドイツのクラフトワークから始まったテクノポップが、ドイツを始めとするヨーロッパ圏に東洋の日本から西還していくのである。
この中田ヤスタカが生んだテクノポップサウンドは、2010年代にはきゃりーぱみゅぱみゅに受つがれることになる。
しかしきゃりーにはファッションのエンターテイメント性があり、ここで言及することは回避させていただきたい。
中田は1993年に聴いたYMOのアルバム『テクノドン』から強い影響を受けたとマスメディアに言及していることからも、CAPSULEからPerfume、きゃりーぱみゅぱみゅなどの一連の流れは、中田ヤスタカのYMOを始めとするテクノポップへのオマージュであると言えるのではないだろうか?
エレクトロ二クス界のビートルズとまでマスメディアで謳われた、元祖であるクラフトワークから始まったいわゆるテクノポップは、20世紀に東洋に伝播して21世紀には西洋、再び世界中に広まったのである。
このテクノポップの文化の灯は、今後ともテクノロジーの発達ととも消え失せる事なく続いていくと筆者は考えている。
日本の理化学研究所は、AIのデジタルシンサイザーでそれに似たことを始めている。


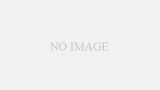
コメント